大河も終わってタッキーお疲れ!ということで・・・。南北朝史跡巡りとして行ったハズが、偶然
義経さんとも重なっていた、だけど枚数的に少ないんだよね〜、というところをまとめて出すこと
にします。
義経さんとも重なっていた、だけど枚数的に少ないんだよね〜、というところをまとめて出すこと
にします。
まずは宮城県の金成町の関連史跡です。金成は金売り吉次の親の墓があるとかいうとこで、
最初に奥州に来たときも義経さんはここを通っているそうです。
最初に奥州に来たときも義経さんはここを通っているそうです。
金成町のパンフです 観光案内図です


パンフの内容を記します。
金成に残る伝説によると、奥州藤原氏のもとへと義経を誘ったのは金成に住む金売橘治。金
成町には、歴史浪漫を裏付けるような旧跡が今も点在しています。
成町には、歴史浪漫を裏付けるような旧跡が今も点在しています。
現在の金田八幡宮一帯は東館跡(とうだてあと)。藤原秀衡の命により橘治が住んだとされる
館跡です。兄弟の橘内は南館、橘六は西館に住んだとされ、義経が秀衡の迎えを待つ間、東
館を訪れたという伝承が残ります。金田八幡宮には橘治が使ったとされる「金運の印」が現
存。義経が東館を訪れた際、お礼として奉納したという匕首と仏像等が保存されています。
館跡です。兄弟の橘内は南館、橘六は西館に住んだとされ、義経が秀衡の迎えを待つ間、東
館を訪れたという伝承が残ります。金田八幡宮には橘治が使ったとされる「金運の印」が現
存。義経が東館を訪れた際、お礼として奉納したという匕首と仏像等が保存されています。
金田八幡宮です。たまたま(道に迷って)ついたところがそうでした(笑)。
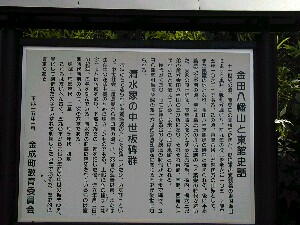
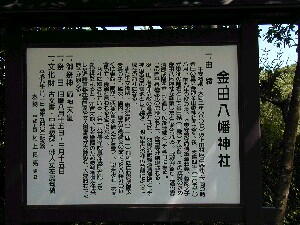
金田八幡神社の由緒書きの内容を記します。
一、由緒
平安初期、大同二年(八〇七)坂上田村麻呂奥州に下向の時金田の里に金神金山彦神社を
祀る。後、天喜四年(一〇五八)八月、前九年の役の頃、陸奥守鎮守府将軍源頼義、義家父
子が東征の陣場として金田城(山城)を築き、その鎮護のために金田八幡神社を勧請したと伝
えられる。戦役が終わり、上洛の際清原成隆を宮司に遣わし、以後連綿として今日に至る。
祀る。後、天喜四年(一〇五八)八月、前九年の役の頃、陸奥守鎮守府将軍源頼義、義家父
子が東征の陣場として金田城(山城)を築き、その鎮護のために金田八幡神社を勧請したと伝
えられる。戦役が終わり、上洛の際清原成隆を宮司に遣わし、以後連綿として今日に至る。
この間平泉藤原氏の庇護のもと、金田寺が創建される。
後、山岳信仰仏教の浸透と共に、羽黒派修験道清浄院として神仏習合の霊地として続き、明
治年代の神仏分離によって現在のお社になる。
治年代の神仏分離によって現在のお社になる。
また平安後期、康治年間(一一四一)畑村に住む炭焼藤太夫婦の子、橘次、橘内、橘六が秀
衡公の命により八幡社の近くに東館、南館、西館の居を構えたという。以来お社一帯を含めて
東館と言われるようになる。
衡公の命により八幡社の近くに東館、南館、西館の居を構えたという。以来お社一帯を含めて
東館と言われるようになる。
お社に残されている第一六世清浄院量海法印が記した参詣帳によると、江戸末期、北方警備
のため奥州街道を往来した近藤重蔵外幕臣達や文人墨客等が大勢訪れ、大変にぎわった様
子が窺える。
のため奥州街道を往来した近藤重蔵外幕臣達や文人墨客等が大勢訪れ、大変にぎわった様
子が窺える。
一、御祀神 応神天皇
一、祭日 旧暦八月一五日、三月一五日
一、文化財 古文書、中世板碑、俳人丈左房句碑
平成九年六月一日 鎮座九四〇年記念祭
奉納 金成上町 村上良亮 建立
左の説明板も似たようなこと書いてるので略します。


義経に関する旧跡が点在する金成。歴史ファンには見逃せない旧跡が沢山あります。南北朝
時代まで血戦の地だった津久茂橋を渡ると、城跡の入り口です。信楽寺跡に「藤原泰衡墓」の
碑文を残す石燈籠があり、その脇道を登ると、義経の身代わりとされる杉目小太郎行信の供
養塔と石碑が建っています。小太郎は身代わりとして自害し、義経を北の地に逃れさせたとい
う「義経北行伝説」の立役者でした。
時代まで血戦の地だった津久茂橋を渡ると、城跡の入り口です。信楽寺跡に「藤原泰衡墓」の
碑文を残す石燈籠があり、その脇道を登ると、義経の身代わりとされる杉目小太郎行信の供
養塔と石碑が建っています。小太郎は身代わりとして自害し、義経を北の地に逃れさせたとい
う「義経北行伝説」の立役者でした。
津久茂城跡の杉目小太郎行信供養塔などです






津久茂城跡にあった説明板の内容を記しておきます。
俳聖芭蕉と奥の細道の旅した弟子の曽良の日記に
「十四日(元禄二年五月ー一六八九)天気吉。一関ヲ立。岩ヶ崎。
真坂。岩ヶ崎ヨリ金成ニ行ク中程ニつくも橋アリ。岩ヶ崎
ヨリ壱里半程。金成ヨリ八半道程。岩ヶ崎ヨリ行ケバ道ヨリ
右ノ方也」と記しているが、芭蕉や曽良の心に映じていた
「つくも橋」とはどんなところであったろう。
吾妻鏡に文治五年(一一八九)八月二十一日、二品(源頼朝)
松山道ヲ経、津久毛橋ニ至リ給フ。梶原平二景高一首和歌ヲ
詠ムノ由之ヲ申ス。
陸奥ノ勢ハ御方ニ津久毛橋
渡シテ懸ン泰衡ガ頸
源頼朝は海、陸、山の三道から二十万の大軍をもって平泉の
泰衡を攻め進んだという。そのころ三迫川沿岸一帯は津浦藻
が生い茂る低湿地帯であった。この藻を刈り敷きつめて全軍を
渡したという時の歌である。
このさき源義経の身代わりになって自殺し、義経をエゾ地に落
してやったという伝説をうんだ「判官びいき義経北行説」の立
役者杉自太郎行信の供養費もこの丘の西に苔むして建っている。
また鬼柳文書によると、南北朝の興国三年(一三四一)九月、北畠顕信
が南朝回天の最後の拠点を津久裳橋城に築き、足利方の将、石塔
義房は釜糠城に陣を張り大合戦を展じている。
以上二つの文献からもつくも橋城附近は奥州の国道であり
血戦の地でもあった。なお赤児部落にある壇の原や乱れ橋も
津久裳橋を中心とした古戦場跡といわれる。
(昭和六十一年三月 金成町教育委員会)
|
|
|


